�@�� �] �� �G �L
���̎G�L��
�@�@�@�ڎ�
�@�@�@�@�@�@���鐢�̑ޔp
2.�@�l���`���ꂱ��
3.�@����̖�
4.�@���̍s����
5.�@�Ӗ��̐[�݂�
6.�@�l�G�A���ɐV���Ȃ�
7.�@�R�[�M���B����
�@�@�@�@�@�@�@���{�̑���
8.�@������l�̈̑�Ȏt
9.�@�C�ӂ̘V�v
�@�@�@�@�@�@�@������ǂ�
10.�@�����j���̋L��
�@�@�@�Z�Z�Z�N��̘`��
�t�^.�@�ʍ؉��r�n�N��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013
11.�@����ǂދ���
12.�@�Y�̍�
13.�@���Z�Z�Z�N��̘`��
14.�@�~���
15.�@�C�s����
16.�@���C�s����
17.�@���̂悤��
�@�@�@�@�@�@�����ꂽ�N�w
18.�@���E��Y�̊Ջp
19.�@�����O���A�O�蔶
20.�@���[�J����Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�h����
19���.�@鰎u���Γ`
�@�@�@�@�@�@�̋����邱��
21.�@�i�����R��ɗ���
22.�@�I�Z�A�j�A�Ƃ͂ǂ�
�t�^.�@�ʍ؉��r�n�N��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2014
23.�@�w���[���b�p���j�x
24.�@�����̍���
25.�@�n�[�o�[�}�X�̓N�w
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
26.�@�s�P�e�B����
27.�@�ӎ��ɏ悹����
28.�@��z���n��
29.�@����m�̕���
30.�@���C�������o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S����
31.�@���R�̐�
32�@���҂�q�˂�
33�@�̑�Ȏt�ւ̎莆
34�@��̏�Ŏ���
35�@���łƃj�q���Y����
�@�@�@�@�@�@�@�@����߂�
29b�@������m�̕���
�t�^.�@�ʍ؉��r�n�N��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2015
36�@���{���_�j��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ǂ�
37�@�Ƃ���ސ��_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ǂ�
38�@�L���ƈ��̓`��
39�@������x��
�@�@�@�R�y���j�N�X�I�]��
40�@���i��
�@�@�@�č\�����邽�߂�
41�@�킽����
�@�@�@�@�@�@�ǂ������҂�
42�@�����̐̌��
43�@�ڊo�߂��l��
�@�@�@�@�@�@����������
44�@�����i���_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�l����
45�@���]�̎���
46�@�������Ƃ����l
46b�@�������̎���
�@�@�@�@�@�ƐS���̐���
47�@�F���ƌ���̗��_
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w��
48�@�V���A
�@�@�@�@�@�w�V���x��ǂ�
38b�@���ƉL��������
�t�^.�@�ʍ؉��r�n�N��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016
49�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̈�
50�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̓�
51�@�ϓ����鎞���
�@�@�@�l�Ԃ�`�������w
�@�@�@�@�\�@�w�閾���O�x
52�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎O
53�@�����Ƃ���
�@�@�@�@�@�������鑶��
54�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎l
55�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌�
�@�@�@�@�@�@�@���̌ܕ��
56�@�푈���̓��L
�@�@�@�@�@�@�@�@��ǂ�
57�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̘Z
58�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎�
59�@�����ŎЉ��T��
60�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̔�
61�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̋�
62�@����Ƃ̓`��
63�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏\
64�@�u���z�̓��v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�l�Êw
�t�^.�@�E�B�g�Q���V���^�C��
�@�@�@�w�_���N�w�_�l�x
�@�@�@�@�@�@��������
65�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@���̏\��
66�@�F���ƌ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@���̏\��
67�@�u���z�̓��v��
�@�@�@�@�@�@���j�n���w
68�@�����ƒ��̑Θb�]�\
�@�@�@���{�̌Ñ�
70�@�C�T�̐l�ӓ��]
�@�@�@�@�@�̐���������
�@�@�����I�Ȋw�̕��@
72�@�Δn�g����
�@�@�@�@�@�@�@�閦
�@�@�@�@�@500�N�܂ł̘`��
�@�@�@�@�@600�N��̘`��
75�@�I��
�@�@�@�V������j����
76�@�C���̖k�ւ̗�
77�@�V����
�@�@�@�n���w�I�����
78�@�킽������炷�Љ�
79�@teatime
80�@�_�召�S�̐l�̕��w
81�@���̒m�V
�@�@�@�@�����ɍl���邽�߂�
83�@���ꐏ�z
�@�@�@�@�����ɍl���邽�߂�
84�@�����ƒ��̑Θb
�@�@�@�@�@�@���ɂ���
85�@�{���u�h�D�[��
�@�@�@�@���@�̑��z�̓�
86�@���p�ɍR��
85b�@�{���u�h�D�[�����@��
�@�@�@���ӎ҂͓��厛�啧��
�@�@�@�m��������
87�@���厛�Ƒ��z�̓�
�@�@�@�@���̐�s���f��
88�@�m�I�ɍ\�����ꂽ
�@�@�@�����u���̖��c��v
89�@�������m��₤
90�@�ꍑ�̓]����
91�@�g���X�g�C�̌|�p
92�@���{�ɂ�����
�@�@�@���ƌ`�����߂�����
93�@�`��������{����
�@�@�@�������̉������_
94�@����
95�@�`��������{����
�@�@�@�̈ڍs��ǐՂ���
96�@���썑�Ƃ̎��@
�@�@�@���厛�̖��������j
97a�@�Ñ�j�ō����
�@�@�@�ɂ��ׂ�����
97b�@���{���͂ǂ�
�@�@�@�悤�ɐ���������
�@�@�@�@�@�@�@�@���_
98�@���E�Ɛl�Ԃ̐�
�@�@�@�ɂ��ā@���̈�
99�@���E�Ɛl�Ԃ̐�
�@�@�@�ɂ��ā@���̓�
100�@
�@�@���s���ɕ{�̗��j
101�@���E�Ɛl�Ԃ̐�
�@�@�@�ɂ���
�@�@�@���̎O�i�f�́j
102�@�w�����̘_���x
�@�@�@�@�@�@���w��
102b�@�w�����̘_���x
�@�@�@�@�@�@��������
103�@���G�n�����Ȋw
�@�@�@�@�@�@��ǂ��
104�@�A�����J��
�@�@�@���E�n�}��ύX
105�@��@�ɂ���
�@�@�@�����c���R�C
106�@�����͂ǂ��
�@�@�@�@�@�@�@���݂�
�t�^�@�u���z�̓��v��
�@�@�@�`���̋������w������
107�@���{�_�b��
�@�@�@�N���ƕϑJ�@�O��
108�@�������Ăɒ���
�@�@�@�@1�D�R��ɗ���
109�@�u����H��
�@�@�@�l�ގj�v��ǂ��
109b�@�������
�@�@�@�@�@�@�@�l�Êw ��
110�@���{�_�b��
�@�@�@�N���ƕϑJ�@���
111�@������ɋN����
�@�@�@�Љ�ƕ����̊v��
112�@�s�r�A
�@�@�@�܂��͌���Q�[��
113�@���
�@�@�@�@�ǂ����痈����
114�@�l�V���̎��{�_
�@�@�@�@�@�@�@����w��
115�@�͔|�C�l�`�d�čl
116�@�w���R�ƗV�Y�x
�@�@�@�@�@�@�@��������
117-1�@�Ȋw�I�F���_
�@�@�@�@�@�@�̍\�� ��
117-2�@�Ȋw�I�F���_
�@�@�@�@�@�@�̍\�� ��
118�@������ӂ�
�@�@�@�@�@�@�o���ϖ�
117-3�@�Ȋw�I�F���_
�@�@�@�@�@�@�̍\�� �O
119�@�w���}���E�w�b�Z��
�@�@�@�@�@�@�w�V�b�_���^�x
120-1�@�x�i����̌���
�@�@�@�@�@�@�Ɠ����̑T ��
120-2�@�x�i����̌���
�@�@�@�@�@�@�Ɠ����̑T ��
120-3�@�x�i����̌���
121�@�l�ސi���ƕ���
�@�@�����̓W�J�͑�����
117-4�@�Ȋw�I�F���_
�@�@�@�@�@�@�̍\�� �l
�@�@�@�u����F���_�v�ᔻ
122�@�Љ�̕ω�
�@�@�ɂ��Ēf�ГI�v��
123�@�s�m�̊C��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
125�@�]�����ɉ���
�@�@�@�@�@�@�r���ɂ����
126-1������Ә_����
126-3������Ә_����
126-2������Ә_����
126-��@.������
�@�@�u������Ә_�v����
127 .���������̋@�\
128 .�S�[�^�}�E
�@�@�@�V�b�_�[���^
�@�@�@�@�@�̊o��
129 .�z�Z�E�I���e�K
�@�@�@�@�@�@�̊i���W
130-0 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z�u�����v
130-1 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��T��
130-2 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��U��
130-3 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��V��
130-4 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��W��
130-5 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��X��
131 .���{�̋ߐ��ߑ��
�@�@�@�@�@�@�v�z�Ƃ̂���
130-6 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��Y��
130-7 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��Z��
130-8 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��[��
130-9 .��`���j
�@�@�@�̍č\�z��\��
132 .�u�}���N�X��
133 .����@�g��
�@�@�@�@�@�v�z�̕ϑJ
134 .�^���̎O�@����
�@�@�@�@�_���̘g�g��
135 .�Љ�Ƃ����Ԃ�
�@�@�@�ق���т����m
136 .�w�p���R��x�Ɋw��
136 .���㎑�{��`��
�@�@�@�@ .�l����
�z�[��
�@�@�@�@�@�@�@ �@�@���@�́@�G�@�L�@���@�@
�@�@�@�Q�O�Q3�N�@�d�q�����w�Ȋw�I�F���_�̍\���@�Ɓu���@�ᑠ�v�ᔻ�x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���A�}�]���ɏo�i���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�p�[�o�b�N�œǂނ��Ƃ��ł��܂��BKindle unlimited ��0�~
�@�@�@�Q�O�Q2�N6���@�����w��͂ǂ����痈�����x�Ƃs�B
�@�@�@�@�@�@��L����������A�}�]���d�q���Љ��B0�~���ǂނ��Ƃ��ł��܂��B
�@�@�@�Q�O�Q2�N�@�d�q�����w���{�_�b�̋N���ƕϑJ�x���A�}�]���ɏo�i���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�p�[�o�b�N�œǂނ��Ƃ��ł��܂��BKindle unlimited ��0�~
�@�@�@�Q�O�Q�P�N10���@�d�q�����u�_�l ���s���ɕ{�̗��j�v���A�A�}�]���ɏo�i�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�p�[�o�b�N�̖{�̌`�œ���ł��܂��BKindle unlimited ��0�~
�@�@�@�w���{���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ����������@�������K�͂���̐��_�x�����
�@�@�@�@�@��d�q���Ђɂ��܂����B�@�@Kindle unlimited ��0�~�œǂ߂܂��B
�@�@�@�Q�O�Q�P�N4��8���@�V���w���{���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ����������@�������K�͂���̐��_�x
�@�@�@�@�@�s���A�A�}�]���ɏo�i���܂����B
�@ �@�w�`���͂����ɂ������@�l���n���w�I�Ș_�x��d�q���Ђɂ��܂����B
�@ �@�u���z�̓��v�V���[�Y�i��64�b�A��67�b�A��69�b�A��73�b�A��74�b�A��75�b�j�������ɂ���
�@ �@�w�`���͂����ɂ������@�l���n���w�I�Ș_�x�i���]�����[�j���o�ł��܂����B
�@�@�@�@�@ �@2025�N�@��133�b�@�|
�@�@2024�N�@��127�b�@�|�@��132�b
�@�@�@�@�@ �@2023�N�@��119�b�@�|�@��126�b
�@�@�@�@�@ �@2022�N�@��108�b�@�|�@��118�b
�@�@�@�@�@ �@2021�N�@��97�b�@�|�@��107�b
�@�@�@�@�@ �@2020�N�@��91�b�@�|�@��96�b
�@�@�@�@�@ �@2019�N�@��78�b�@�|�@��90�b
�@�@�@�@�@ �@2018�N�@��65�b�@�|�@��77�b
�@�@�@�@�@ �@2017�N�@��49�b�@�|�@��64�b
�@�@�@�@�@ �@2016�N�@��36�b�@�|�@��48�b
�@�@�@�@�@ �@2015�N�@��23�b�@�|�@��35�b
�@�@�@�@�@ �@2014�N�@��11�b�@�|�@��22�b
�@�@�@�@�@ �@2013�N�@��1�b�@�@�|�@��10�b
�@���͖����鐶�����ł���B�Ñ㒆���̓N�w���Ƃ�������ÓT�w���q�x���A���łɌ���
�ɘ_���Ă���B�u�킽�������͖��Œ��ɂȂ���(����)�y�����A������o���킽����
�ʂ��đ����Ȃ̂�����Ƃ����̖��̒��̐l���Ȃ̂��v�A�����f�肷�邱�Ƃ͂ނ�
�����ƁB���̓T���ɂ���ē��{�̔o�l�́A���𑑎��ƕ\������B���������Ƃ�����g��
��^�����ꂷ���Ă��邯��ǂ��A���̔�g�͐l�������Ƃ����傫�ȉB�g���݂����
����̂ł���B�l�́u�l���Ă��鎩��������v�ƈӎ�����B�Ƃ��낪�A�����̋@��Ɏ���
�̐l���𗣂ꂽ�Ƃ��납��ς銴�o���N���Ă���Ƃ��A���̑z�N�������̈ӎ�����V��
���Ă���悤�Ɋ����āA���Ƃ������t��A�z����B������ł��I�݂Ɍ�����̂�������
���b���낤�B�����悤�ɌÍ������̌��l���A�l�������̂ɖ��Ƃ������t���g���Ă���B
���Ƃ����[���b�p�ł͂v�E�V�F�C�N�X�s�A���A�u�����͖��Ɠ������̂ŏo���Ă���B
�����Ă����̒Z���ꐶ�́A����ƂƂ��ɏI���v�ƕ\�������B���{�ł��A���l�ƌ���
�邩�ǂ���������Ȃ����A�������������l�������̋�Łu��g�̂��Ƃ����̂܂����v��
�r�B���m��̐l�́A�l���Ɩ������т��閼����������ł������邱�Ƃ��ł���
���낤�B
�@���E�����E���Ƃ����A���́A�����Ȓ��ɁA�_�o��H�����炷���Ƃ������̂����B����
�āA�ӂ�ӂ炵�����͎��Ɏx���ŗ�Ȗ��z��a�����ƂɂȂ�B�����A�g�H����䔒����
�疼���Ȃ������Ȓ��܂ŁA���̎����قɂ��Ă��邪�A�����������Ȃ钱�ł���������
�킫�܂��Ȃ��҂̒��ɁA�����𑑎��Ɏ������������o��͖̂����鐶�����̐���
���낤���B�����ɁA���̈̑�Ȑl��^���āA���Ƃ߂��Ȃ����������U�炻���Ƃ���҂�
����B�w���q�x�𑑎��̎G�L�����ƍl����̂��B��������Ȏv���Ⴂ���������́A
�����e�[�j����̎傪�Ă��ď������̂������悤�ȎG�L�����Ɖ��߂�i�߂�B�Ȃ�Ƃ���
���Ƃ��낤�A�������E�ɂ��т���L���Ȏv���̏��ɂ�������āA�����̒��ɂ��G�L����
������ƌ֑�ϑz����̂ł���B���ɂ��̒��ƂȂ��Ă���킽���́A�f���I�ɕ�����
��������z�O�ɂ����Ƃ����Ă���A����ӂꂽ�v���ł����͂ɕ\�����邱�Ƃ�
�v���ɋ߂Â��C���ŁA�Ђ���Ƃ�����Ӗ����ނ��Ԃ�������Ȃ��Ɗ��҂��āB���̒���
���ɂȂ邱�Ƃ�����Ƃ���A���̋��ɒp�����邱�Ƃ��낤……�B
�@���̍�Ƃ��������̂܂����ɂȂ邾�낤���ƂΈӎ����B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013�N����
�@���K�ҁ@
     |

************************************************************************
�@137�@�֖��ȘV�l�����㎑�{��`���l����
************************************************************************
�@136�@�w�p���R��x�Ɋw��
************************************************************************
�@135�@�Љ�Ƃ����Ԃ��ق���т����m
************************************************************************
�@134�@�^���̎O�@���Ɨ��_�̌n�̂��ׂ��_���̘g�g��
************************************************************************
�@133�@����@�g�̎v�z�̕ϑJ
************************************************************************
�@132�@�u�}���N�X�̐V�������ݘ_�v�ᔻ
************************************************************************
�@130-9�@�Ñ�`���j�̍č\�z��\��
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@700�N�ォ��̓��{���̂��Ƃ́A�w���{���I�x�̎��́w�����{�I�x��
�@�@�@�@������Ă���B�����̐l��700�N�ォ��̂��Ƃ݂͂Ȃ悭�������Ă���
�@�@�@�@�Ǝv���Ă��邯��ǂ��A�w�����{�I�x��^���ɓǂ߂A���̓��{���ɂ�
�@�@�@�@�O�j�����������Ƃ����炩�ɂȂ�B
�@�@�@�@�����āA���{�̌Ñ�j������ς��ė���������B
�@�@�@�@�@�ɐ��̍c��_�{�͕����V�c�̂Ƃ����Ă�ꂽ���A����ȑO��
�@�@�@�@�u���z�̓��v�̐_�a�͋�B�̉F���{�������B��������サ���̂��B
************************************************************************
�@130-8�@�Ñ�`���j�̍č\�z��[��
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�w�������x�́A2�̐߂ɕ����Ę`���Ɠ��{���Ƃ�ʁX�ɋL�q���A
�@�@�@�@�@�@2�̍����قȂ鍑�Ƃł���ƔF�����Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�@���̎�����ے肷�邱�Ƃ͒N�ɂ��ł��܂���B
�@�@�@�@�@�@���{�̗��j�Ƃ́A���̖���������Ȃ�������Ȃ��̂ɁA
�@�@�@�@�@�@����܂Ő^���ɍl�����l�͂��܂���A������l�������āB
************************************************************************
�@130-7�@�Ñ�`���j�̍č\�z��Z��
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@��Z�́@600�N�㏉���̘`��
�@�@�@�@�@�@�@�w�@���x�́A�@�g�̗����`�����ǂ��ɂ��������A
�@�@�@�@�@�@�@�n���ɂ܂��ꂪ�����Ȃ����x�ō����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@���N��������̋������Ŕ�r����A�w�O���u�x�̎w����
�@�@�@�@�@�@�@��v���܂��B���@�߁A�}�Z.1�Ɛ}�Z.2�B
************************************************************************
�@130-6�@�Ñ�`���j�̍č\�z��Y��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Õ�����̘`��
************************************************************************
�@131�@���{�̋ߐ��ߑ�̎v�z�Ƃ̂���
************************************************************************
�@130-5�@�Ñ�`���j�̍č\�z��X��
�@�@�@�@�@���悢���ɓ���A
�@�@�@�@�@4�̎���A�퐶����E�Õ�����E600�N�㏉���E600�N��
�@�@�@�@�@�ɕ����āA���ゲ�Ƃɘ`���̋�̓I�ȗ��j�ɐ荞�݂܂��B
�@�@�@�@�@�e�͂̂قƂ�NJe�߂��ƂɁA�����̐l�����߂ĕ����悤�Ș_�_����A
�@�@�@�@�@�V�����_����܂��B
�@�@�@�@�@���̑�X�͂́A������"�הn�䍑�_��"���ӂ��Ƃ��A
�@�@�@�@�@�ڂ������菜���āA�V�������E���J���ł��傤�B
************************************************************************
�@130-4�@�Ñ�`���j�̍č\�z��W��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ꂽ���j�����ɐ荞�ނ��߂�
************************************************************************
�@130-3�@�Ñ�`���j�̍č\�z��V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�ł̐��c���̓��i�Ɩk�i
************************************************************************
�@130-2�@�Ñ�`���j�̍č\�z��U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���̓`�d����w��
************************************************************************
�@130-1�@�Ñ�`���j�̍č\�z��T��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z���q�l���u���z�̓��v�Ɨ��j�I�ω�
************************************************************************
�@130-0�@�Ñ�`���j�̍č\�z�u�����v
************************************************************************
�@129�@�z�Z�E�I���e�K�̊i���W
************************************************************************
�@128�@�S�[�^�}�E�V�b�_�[���^�̊o��
************************************************************************
�@127�@���������̋@�\
************************************************************************
�@126-��@�����́u������Ә_�v����
************************************************************************
�@126-2�@������Ә_����l�ԂƎЉ���l����(��)
************************************************************************
�@126-3�@������Ә_����l�ԂƎЉ���l���� �t�^
************************************************************************
�@126-1�@������Ә_����l�ԂƎЉ���l����(��)
************************************************************************
�@125�@�]�����ɉ����r���ɂ����
************************************************************************
�@123�@�s�m�̊C�ɋ�����
************************************************************************
�@122�@�Љ�̕ω��ɂ��Ēf�ГI�v��
************************************************************************
�@117-4�@�Ȋw�I�F���_�̍\�� ��_�F�u����F���_�v�ᔻ
************************************************************************
�@121�@�l�ސi���ƕ��������̓W�J�͑�����
************************************************************************
�@120-3�@�x�i����̕��������Ɠ����̑T�O
************************************************************************
�@120-2�@�x�i����̕��������Ɠ����̑T��
************************************************************************
�@120-�P�@�x�i����̕��������Ɠ����̑T��
************************************************************************
�@119�@�w���}���E�w�b�Z�́w�V�b�_���^�x
************************************************************************
�@117-3�@�Ȋw�I�F���_�̍\�� ���̎O
************************************************************************
�@118�@������ӂƌo���ϖ�
************************************************************************
�@117-2�@�Ȋw�I�F���_�̍\�� ���̓�
************************************************************************
�@117-1�@�Ȋw�I�F���_�̍\�� ���̈�
************************************************************************
�@116�@�w���R�ƗV�Y�x��������
************************************************************************
�@115�@�͔|�C�l�`�d�čl
************************************************************************
�@114�@�w�l�V���̎��{�_�x����w��
************************************************************************
�@113�@��͂ǂ����痈������2��
�@�@�@�@�@�@�C��n���w�I�Ȑ��_�@�@�@�@�@�u���̎G�L��113�v
�@��L�̂悤�ȃ^�C�g���ŏ����ȏ��������܂����B2016�N�ɋL�������̎G�L��
�u38��38b�v���A����ɂ��܂��܂ȕ����ׂċc�_�𑍍��I�Ȃ��̂ɔ��W������
�_�l�ł��B��̓`�d�ɂ��Ă���܂łɏ����ꂽ�ޏ�������e�����A
�Ǝ������Ă��܂��B���̘_�l�́A2012�N�ɐ����w�I��DNA�̉�͂ɂ���āA
�͔|�C�l�̋N���n��������[���̍L���`������������𗬂���]�������
���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����������ʂɊ�Â��Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�����Ă���
�������̑��ł͍��ł���͔̍|�͒��]��������Ŏn�܂����A�Ə�����Ă��܂��B
����͉��߂��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�V���������́A������[������C�l���ܓx�������x���z���Ėk�サ���Ɨ�������
���Ƃ�v�����܂��B���̘_�l�́A���R�Ȋw�̘_���̂悤�ɁA��ЂƂf�[�^��
�؋��������Ę_����g�ݗ��āA�C�l�̖k���i�K�I�ɐ������鑎���I�ȗ��_��
��N���܂��B���̕��@������I�Ȃ̂́A����܂ōl������Ă��Ȃ��������ƁA
���Ȃ킿�A���ł���C�l�̐���ōŏd�v�ȋC����������čl�������Ƃł��B
�C�l������y�n����ʂ̓y�n�Ɉړ�����Ƃ��̋C��̍����A�����Ƃ̕���
�ō��Œ�C���ƍ~�J�ʂƂ������l�f�[�^�ŕ\�����ċc�_���܂��B����ɂ���āA
�͔|�N���n����C�l���ǂ̂悤�ȃ��[�g��ʂ��Ėk�サ�A�ǂ�������{��
�n���Ă������A����܂łɂȂ��m�x�̍������^�����܂��B
�@���̋c�_�̃n�C���C�g�����̃O���t�Ŏ����܂��傤�B
�@�@�@�@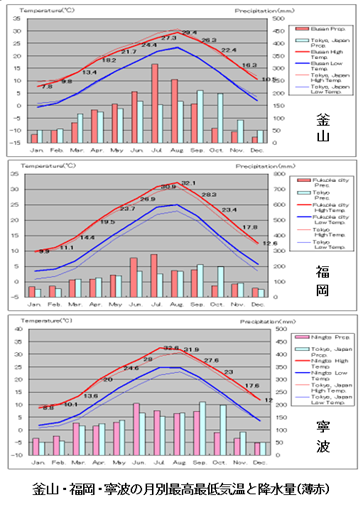
���̃O���t�����āA���Ȃ��́A�����̍l�Êw�҂̌����悤�ɒ��N�������痈��
�Ǝv���܂����A����Ƃ����]������̍Y�B�p�݈�i�J�g�͂����ɂ���܂��j����
�C��n���Ă����Ǝv���܂����B
�@���킵�����e�́A�A�}�]���ɏo�i���������w��͂ǂ����痈�����x�ł��ǂ�
���������B�������Ċ��҂����炬�邱�Ƃ͂Ȃ��͂��ł��B
�@�Q�l�̂��߂ɁA�{�̖ڎ��������Ă����܂��傤�B
��P�́@�����{��̓`�����[�g --------------------- 1
��Q�́@���{�̍l�Êw�����肷��͔|�C�l�̓`�����[�g- 5
��R�́@�Ñ㒩�N�����̓ˑѕ��y��Ɩ����y�� --------9
��S�́@�Ñ�̒����k���E���N�����ł̈��P------- 13
��T�́@�Ñ�̒����k���E���N�����ł̈��Q------- 21
��U�́@�����w���猩���͔|�C�l�̓`�d ------------- 31
��V�́@�C��n���I�ϓ_����̑����I�ȋc�_ --------- 38
�@�O. �{���̋C��n���w�I�ȕ��@ ------------------- 38
�@�T. �g�����W���|�j�J�h���k�サ���n�� ----------- 48
�@�U. �͔|�C�l�̒��]���悩��`��-�̉͐����z����k��48
�@�V. �͔|�C�l�̎�]���悩�璷�]����ւ̖k�� ------55
�@�W. ��]����ƃC���h�V�i�����ŋN�������� --------60
�@�X. �M�уW���|�j�J�c��n���̊g��`�d ------------65
�@�Y. �������k���ƒ��N�����ւ̃C�l�̓`�d ----------77
��W�́@�C�l�̓��{�ւ̓`���Ƃ���Ȃ�`�d ----- 91
�@�T. �ǂ����痈�ē��{�֏㗤������ ----------- 91
�@�U. �C�l�̓��i -------------------------------- 97
�@�V. �C�l�̖k�i ------------------------------- 102
��X�́@���c���Љ�̕������� ----------------- 108
�@�@�D�L�� ------------------------------------ 108
�@�A�D������ ---------------------------------- 111
�@�B�D���Љ�̕��������������炵���l�X ------- 113
�Q�l�����@�@----------------------------------- 121
���Ƃ����@�@----------------------------------- 125
�u���Љ�̕��������������炵���l�X�v�]�b
�@��X�͂��B�u���Љ�̕��������������炵���l�X�v�̂Ƃ���ɁA���{�̗��j��
�W���邱�ƂȂ̂ŁA���̂悤�ȕ���������U�f�ɂ����܂����B�������A�֑���
�`���Ę_�l�S�̂̐��_�̎��𗎂Ƃ����Ƃ�������āA�Ƃ��߂܂����B���̕���
�o���Ƃ��Ă����ɋL�^���Ă����܂��傤�B
�@���̘_�l�ł������ł������A�̂́g�����h���ǂ��ĂԂ��ɂ͔Y�܂���܂��B
�g�����h�ł͑�X���������������āA���̖��ŌĂԂ��Ƃ����Ⴞ�����̂ŁA
�����ň��肵���Ăі����ʗp���邱�Ƃ͖W�����܂����B�O������g�����h��
�̈���w���ČĂԖ��́A�����̕ω��ɉ����ĕς�����킯�ł͂���܂���B
�Ñ�C���h�ł́g�����h�̌Ăі��́A���T�̊����\�L�u�x�߁v�ɂ����
�m���邻���ł��i����́A�Ñ�̍��Ɩ��u�`�v���炫���̂��낤�ƍl�����
�Ă��܂��j�B�Ȍ�A���̏����ł����悻����Ǝ��������ŌĂԂ��Ƃ�������
���Ƃ��A����̉p�ꖼ�uChina�v�������܂��B
�@�̂̓��{�ł́A�g�����h���u���낱���v��u����v�ȂǂƌĂт܂����B�����������
�\�킷�Ƃ��́u���z�v��u���y�A���邢�͓��v�Ə����܂����B���A�W�A�ɂ�����
�����̋����e�������������ꂽ���̂́A������Ƃ͉��C�̌n��
�傫���قȂ�̂Ŏ����̂��ƂĂČĂ��̂ƍl�����܂��B���̌Ăі���
�ʗp����āA�g�����h�̉�������サ�č������ς���Ă��A�Ăі���ς���
�����\�L�����̂܂g�p�����̂ł��傤�B
�@�Ƃ���ŁA�u���낱���v���w���{��S�ȑS���x�́u���y�v�Œ��ׂ�ƁA�u���y�v��
�ǂ݁u���낱���v�́u���z�v�̌P�ǂ݂��炫���ƍl�����A���́u���z�v�́u�S�z�v
�Ɠ��`���A�Ə����Ă���܂��B���̉���͂����炩�u���{�ƒ����̌𗬎j�v��
�����܌����A�킽�����v���ɗU���܂��B
�@���x�́w��͂ǂ����痈�����x�ŁA�����{�ɂ����炵���l�X�͍Y�B�p�݈�
���痈���W�R���������A�u�S�z�v�̂Ȃ��ł��t�H�퍑����ɐ����������u�z�v��
�n��̐l�X�ƌ����Ă��傫�Ȍ��ł͂Ȃ����낤�A�Ƙ_���܂����B���́u�S�z�v��
�u���z�����낱���v�̂��Ƃ��Ƃ���ƁA���������z����c��܂��邱�Ƃ��ł��A
�����𗬎j����̓`���̂���ɂ܂ŊO�}���čl���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B
�������A�w��͂ǂ����痈�����x�ɂ��������悤�ɁA����^�l�X���ǂ�����
�������͓`���Ƃ��Ă��`���Ȃ��̂ŁA�m�x�̍����b�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����B
�@�u���z�v�Ƃ������Ƃ́A�w���q�x�u疗y�V���v�ɏo�������Ƃ���������ł��B
�����ɂ́A�u�v�l�A�͕�����Ƃ��ď��z�ɂ䂭�B�z�l�͒f�����g�ɂ��āA�����
�p���鏊�Ȃ��v�Ƃ����ꕶ������܂��B�v�̐l���v�̖��Y�͕̏�Ƃ�������������
���z�ɔ���ɍs��������ǂ��A�z�l�͒f�����Ă���̂Ŋ����g���l�����Ȃ������A
�Ƃ����̂ł��B��g���Ɂw���q�x�ł́A�u���z�v�Ɂu���傦�v�Ƃӂ肪�Ȃ��ӂ���
����܂��B���̂��Ƃu�������̉z�v�́A�z�l�̂��鏔�n���Ƃ����قǂ̈Ӗ���
�Ȃ�ł��傤�B�����ł́u�z�l�͒f�����g�v�Ƃ��Ă��āA�w�O���u�x���`�l��
�u�j�q���召�F�|�ʕ��g�A�c�A�č@���N�V�q������m�A�f�����g�A�c�A
���݉�m����V���v�Ə����̂ɑΉ����Ă��܂��i�w��͂ǂ����痈�����x�̖{���ł�
���̕��ɐG��܂����j�B�ł�����A�u���z�v�͂������̉z�l�̂���L���n���
�w������ǂ��A�f�����g�Ƃ������Ƃ���m������̉z�l�ɏœ_�ĂĂ���A
�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�w�O���u�x�́A�f�����g�̂�������m�̐l��
�u倗��V�Q������邽�߁v�Ƃ��A����ƕ�������悤�ɁA�u�`�̐��l�͍D���
�������ċ�����ߊl���邪�A���g�͑勛���ׂ��������邽�߁v�Ə����Ă��܂��B
�`�l�Ɖ�m������̉z�l�Ƃ̂Ȃ�����������Ă���̂ł��B
�@�w���q�x�u疗y�V���v�̘b���番����悤�ɁA�u���z�v�͒��]���������̗̈��
�w���܂��B��m�Ƃ����n���͍��̏Ћ��s�𒆐S�Ƃ���Y�B�p�݈���w���A�Â�����
���̈�т́u�z�v�ƌĂ�܂����B���ł����]���悩���̗̈�̓`��������
���̂��āu�z���v�Ƃ������Ƃ��g���܂��B�Ƃ�킯�Y�B�p�݈�ɂ͊C�ɐe����
�l�X�������̂ł��B�����āA��Ɏ������O���t�̈�ԉ��̔J�g�͂��̒n���
����܂��B�ł�����A�u���낱���v�Ƃ����Ăі��́A��͂��̍Y�B�p�݈�̊C��
�Ȃ��l�X���D�ʼn^��ł����Ƃ����{���̐���ƁA��������̂ł��B
�@��̂��Ƃ͓����𗬎j�̑O�j�ƌ�����Ǝv���܂����A���������������ŁA
�̂̓��{�l���g�����h���u���낱���v��u����v�ȂǂƌĂo�܂�T���Ă݂܂��傤�B
�u���y�v�Ə����āu���낱���v�ƓǂނƂ��������ƁA�u���낱���v�Ƃ����Ăі���
��ɂ������ƍl�����܂��B
�@�u���낱���v���u���z�v�̓��{��ǂ݂��Ƃ���A���̎���ɑ嗤�ƍs��������
�`�l�́u���z�v�ƌĂ��n��܂蒷�]���������̗̈�ɍs���Ă����A
�Ƃ��������Ɏ���܂��B�Ƃ��낪�A�`�l�������̗��j���ɋL�^�����悤�ɂȂ���
�̂́w�㊿���x��w�O���u�x�ŁA�������ΏۂƂ�������̌㊿�E鰂Ɓw�O���u�x��
�����ꂽ�W�̓s�͗��z�ɂ���܂����B���z�́u���z�v���������Ɩk�ɂ���܂��B
���̎���Ɂg�����h���u���낱���v�ƌĂƂ���ɂ͖���������܂��B�@����ƁA
�`�l���g�����h���u���낱���v�ƌĂ̂͂���������̂��Ƃł��傤�B
�g�����h�Ɩ{�i�I�ɍs���������ŏ��́A400�N��̘`�̌܉��̎���ł��B
���z�����z�����W����ēs�����N�Ɉڂ������W�ƁA���̂��Ƃ̑v�E�āc�̓쒩��
����ł��B���̎���͒����������ǂ��Ɠ����Ă�������ƌ������Ƃ��ł��܂��B
���{�Ŋ����̔����́u�����v�Ɓu�����v�̓�ɑ�ʂł��܂����A�u�����v�͂�
�̎���ɓ����Ă��܂����B���̎���̘`�l���A�g�����h���u���낱���v�ƌĂ�
�Ƃ����������ł��܂��B
�@���Ɂg�����h�Ƃ̌𗬂�����ɂȂ����̂́A�@�E���̎���ł��B�`�����@�Ɏg�߂�
�h�������͓̂�x�ŁA�܂��Ȃ��@�͖łтĂ��̂��Ƃ̂��Ȃ蒷�����������Ƃ�
�s����������ł����B���̎���A�g�����h�������́u���v���邢�́u���y�v�Ə�����
�̂ł��B��Ȃ��ƂɁA�w���{���I�x�́u��22�v�ŁA�@�Ƃ̎g�߂̉������L�q����
�̂ɂ��A���葤���u���v�Ə����Ă��܂��i�@�Ƃ����������o���Ȃ��w���{���I�x��
�������͗��j���̋L�q�Ƃ��Ė����͂��ł��܂����A�����Ă�����
����܂���B�w���{���I�x�ҏC�����̊���Łg�����h�����u���v�ƌĂ�ł��܂����A
�ƌ�������Ă���̂ł��傤���A����ȏ�̎���B����Ă���Ƃ��l�����܂��j�B
�Ƃ������A���x�������g�𑗂����u���v�����{���ł悭�m����悤�ɂȂ��āA
�u���v�Ƃ��������\�L����ʓI�ɂȂ����̂ł��B����ł��A���́u���v���A����ȑO��
�Ăѕ��Łu���낱���v�ƌĂԂ��Ƃ���ʓI�����̂ł��傤�B�u���v���u����v�ƌĂԂ̂́A
���ƂɂȂ��Đ������A�ƍl�����܂��B
�@����肠�ƁA�g�����h���琳���̎g�҂������̂́u���v�̎���ł����A����ȑO
�̑v�̎���ɂ������Ԃ̌��Ղ͑����Ă��܂����B���ȗ��A���{�ł́A�u���낱���v
���邢�́u����v�Ƃ����Ăі�������ɂȂ��Ďg��ꂽ�̂ł��B
�@�b���U���ɂȂ��Ă��܂��܂������A������L�����̂́A�`�̌܉��̎����
�`�l�́A�u���z�����낱���v�ɍs�����Ƃ��A���������̐�c�ɂ����̉z�l�Ɠ���
�u�|�ʕ��g�v��u�f�����g�v�̕��K���������ƒm���Ă������낤���A�Ƃ����^���
����������ł��B�܂��A�`���͋L�^����Ȃ���������ǂ��A�Â�����ɂ́A
�u��ǂ����痈�����v����Ă������낤���A�Ƃ������҂����߂��^���
����������ł�����܂��B
�@�@�@�@2022�N6�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���@�J��C
************************************************************************
�@112�@�s�r�A�܂��͌���Q�[��
************************************************************************
�@111�@������ɋN�����Љ�ƕ����̊v��
************************************************************************
�@110�@���{�_�b�̋N���ƕϑJ�@���
************************************************************************
�@109b�@����Õ��̍l�Êw ��
************************************************************************
�@109�@�u����H��l�ގj�v��ǂ��
************************************************************************
�@108�@�u�������āv�ɒ��ށ@1�D�R��ɗ���
************************************************************************
�@107�@���{�_�b�̋N���ƕϑJ�@�O��
************************************************************************
�@�t�^�@�u���z�̓��v�͘`���̋������w������
�@�@�@�@���̍e�́A�����q�̑�w�Z�~�i�[�n�E�X�ŊJ�Â��ꂽ
�@�@�@�@�u�Óc���F�L�O�Ñ�j�Z�~�i�[�v�ł̍u�����e�ł���B
�@�@�@�@����ɂ́A����܂ł̒�����u���̎G�L���v�Ŏ����Ă��Ȃ�
�@�@�@�@�}���������܂܂�Ă���̂ŁA�t�^�Ƃ��Č��J����
�@�@�@�@���̃Z�~�i�[�͌Óc���F����̊w����M��l�����̉
�@�@�@�@�����ŊJ�Â������̂ŁA�����̉�ɏ������Ȃ��킽���́A
�@�@�@�@��ѓ���Ŕ��\����@���^����ꂽ�B
************************************************************************
�@106�@�����͂ǂ�ȑ��݂��@�����̓Ƃ茾
************************************************************************
�@105�@��@�ɂ��鑺���c���R�C
************************************************************************
�@104�@�A�����J�����E�n�}��ύX
***********************************************************************
�@103�@�w���G�n�����Ȋw�x��ǂ��
***********************************************************************
�@102�@�w�����̘_���x���w��
�@102�t�^�@�w�����̘_���x��������
************************************************************************
�@101�@���E�Ɛl�Ԃ̐��ɂ��ā@���̎O�i�f�́j
************************************************************************
�@100�@�`�����{���������_���J�����E
�@�@�@�@���s���ɕ{�̗��j
************************************************************************
�@99�@���E�Ɛl�Ԃ̐��ɂ��ā@���̓�
************************************************************************
�@98�@���E�Ɛl�Ԃ̐��ɂ��ā@���̈�
************************************************************************
�@97�@���{���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ����������@�����ƌ��_
�@�@�@�@���̍e�́A�������̏����w���{���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ���������
�@�@�@�@�������K�͂���̐��_�x�̏����Ƒ�W�́u���_�v�ɓ�����B
�@�@�@�@��T�́A��U�́A��V�́A��_�́A���́u���̎G�L���v�ŁA
�@�@�@�@92�A93�A95�A96�Ɏ��^���Ă���B
�@�@�@�@����97a�������́A97b�����_��PDF�t�@�C���ł���B
�@97a�@���{�̌Ñ�j�ō����ɂ��ׂ�����
�@97b�@���{���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ����������@���_
************************************************************************
�@96�@���썑�Ƃ̎��@���厛�����������j
************************************************************************
�@95�@�`��������{���ւ̈ڍs��ǐՂ���
************************************************************************
�@94 �����@�@���ƍ��ƂƂ����������z
************************************************************************
�@93�@�`��������{���։������̉������_
************************************************************************
�@92�@���{�ɂ����鍑�ƌ`�����߂�����
************************************************************************
�@91�@�g���X�g�C�̌|�p
************************************************************************
�@90�@�ꍑ�̓]����
************************************************************************
�@89�@�������m��₤
************************************************************************
�@88�@�m�I�ɍ\�����ꂽ�����u���̖��c��v
************************************************************************
�@87�@���厛�Ƒ��z�̓��A���̐�s���f��
************************************************************************
�@85b�@�{���u�h�D�[�����@�̔��ӎ҂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���厛�啧��m���Ă�����
************************************************************************
�@86�@���p�ɍR��
***********************************************************************
�@85�@�{���u�h�D�[�����@�̑��z�̓��@ 2019�N9��20������e
************************************************************************
�@84�@�����ƒ��̑Θb�@���ɂ���
************************************************************************
�@83�@���ꐏ�z�@���[���b�p�̏�����
************************************************************************
�@82�@�g�S�Ƃ��Ă���l�Ԃ̐�
************************************************************************
�@81�@���̒m�V�@�����ɍl���邽�߂�
************************************************************************
�@80�@�_�召�S�̐l�̕��w
************************************************************************
�@79�@teatime PDF��
�@�@�@�@���N�́A�_���̌����������߂���l�@�����Č����Â����B���ۂɍ��r�����܂łɒɂ݂������A
�@�@�@����҂��A�O�̂��߂ɂƊj���C���̉摜�܂ŎB�点����ł�f�@�����B�����Ƃ��A���Ȑf�f�ł�
�@�@�@�ւ��ȑ̑��̂����������Ǝv���B���������킯�ŁA����͌����ق������߂ɂ����̎��Ԃɂ��悤�B
�@�@�@���N�A�l�������t�ő����ܓ�������̌����Ƃ����߂ł�����ɂ߂������B���̂Ƃ�����
�@�@�@�|�������̂������ŁA�ƂĂ��y�������Ԃ��߂������Ƃ��ł����B����́u�G�r���L�v�ɏ������Ă��邪�A
�@�@�@���N�̊��������Ɋ�������Ƃ��Ă��N���ɂȂ�̂ŁA�����ɐ���̊y���݂��L���Ă����B
�l�����t
�@��ӁA�N�������̂��߂ɗ���̏��Ɂu�t����я��X��v�Ƃ����|������
�������B���Ă킽�����A�\���~�̏��̊ԂɁu�t���b�����ߗ��v�̎����|����B
���̒W���͗l�̏�ɗꏑ�̂ŏ����ꂽ���ŁA�ܕ����ڂ́��͑O����ǂ߂Ȃ���
�����Ă����B�����͎v�������ăC���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂āA�摜�̏W�܂�̒���
���������̋���������B��͂�A�u�ˁv�̎��`�Łu�H�v�̕������u�ځv�Ə����Ă���B
�����A�������ďo�Ă���̂͒�����ŏ����ꂽ�L������ŁA�܂��ǂ߂Ȃ��B
�ڂ��ڂ��Ă����ƁA�n�Ղ��Љ���炵�����Ɂ����u���v�Ƃ�����̂��������B
���́u���v�̎���������Ȃ��B�摜�ɏo�Ă������ɂ͂��̎����ƑɂȂ��
�u�[�z���t�����ʁv�����ׂĂ������B���́A�킪�Ƃɂ͂�����̋�̊|������
�����āA��̊|�������c�z�ł���������̂ł���B�u���ʁv���u?��v�Ə������
���邯��ǂ��A?����(�J���X)�ّ̈̎��Ƃ������Ƃ�����A���ӂ͓����ł���B
���t�ɁA�u�t���b�����ߗ��v�̕��������|�����̂́A�u�[�z���t��?��v���H��
��ۂ�^����悤�Ɏv��������ł���B
�@�T���͂������낢���ʂ������炵���B���̑�͂��Ƃ��ƌh������h�g��
���̎��ɂ������̂��B
�@�@����@�s�p���D�|�����@�@�F�P���q�|����
�@�@�@�@�@�V���ꉍ�҉M���@�@���J���l�s����
�@�@�@�@�@�t���b���Œߗ��@�@�[�z���t����|
�@�@�@�@�@�����O�O���A�e�@�@���F�ƎR��{��
�@�@�@�@���F��l��A���J�͐̂Ȃ��݁B�攪��A�ƎR�͂ӂ邳�ƁB
�@�����l�����i����|���j�ʼn��C����A��̗����̂����̑�
�����A���`�[�t�ƌ`�����߂�������f���Ă������B
�@�@����@�V�������u�C���@�@���������쎍��
�@�@�@�@�@�V�U�ߊ����l���@�@�d�H�P�ӉߋS��
�@�@�@�@�@�O���ߜ�v��樁@�@�ǒ��I���͋�|
�@�@�@�@�@�T�ߙ����͌��ā@�@���w�V?��㌳
�@�@�@�@�@���F�C���^�[�l�b�g�ɂ��ƁA��܋����樂͑O���̐l�A���͓͂̉���ς��邱�Ƃ�����A
�@�@�@�@�@�̂��ɍ��J���ꂽ�������B��Z��̋�|�͑����Ɏd���A�h�g�Ɠ����悤�ɓ���ɗ����ꂽ�B
�@�@�@�@�@�͖Ƃ��悤�Ƃ����Ƃ��ɂ͂��łɖS���Ȃ��Ă����̂ŁA�q�炪�Ƃ肽�Ă�ꂽ�Ƃ����B�掵�E����́A
�@�@�@�@�@�߂������ꂵ�ē���ŗL���ȕĂɕς��A���̏o���オ�鏬�������w�܂萔���đ҂��Ă���
�@�@�@�@�@�悤�����r���B
�@���̎��Ō��̎��́u�Łv��“��”�ɕς����͎̂��̋�́u�[�v��
�ΏƂ������ƌ�����B���ꂾ�ƁA���͒��Ɨ[�ׂ̏�i���̂����ƂɂȂ�B
�Ƃ���ŁA���̎��́A�u�t���b�����ߗ��v�̋���L�B�[���[�h�ɂ��Ē������
�u�ۊ�Ɂv�Ō��������̂����A�u�[�z���t����|�v�̋�ɂ��T���͂������
�����������B���̓�?�Ƃ����l�̎��u���ǎR��珏M��v�ŁA��܁E�Z���
�u��|���t�[�z���A�뗧�b�ԏH�����v�Ƃ������B�h�g�̎��͖{�̎������Ă���
�̂ł���B�l���Ă݂�A�������a�̂Ɠ������̂̏G���ϑt���邱�Ƃ����Ă����B
�v����̎��l�Ƃ����h�g�͋��{���[���A���R�ɌË���r�ݍ��ނ��Ƃ�������B
��̎����r����A���͏H�̎����������̂��A�h�g���t�̎��ɕς������Ƃ�
�m����B���̎�������ꂽ�̂�1100�N���A���z��̐��������ƕ������Ă���B
�ꏊ�͊C�쓇�B����̟F�P��������悤�ɂ����͈��M�тɂ���B�h�g������
�͍̂�ł͂Ȃ��Ē߂̈��ŁA�u���v���g�t�����Ƃ͈Ⴄ��������Ȃ��B
�ނ���A�h�g�͂��̏�̎��i���r�̂ł͂Ȃ����B�u�Łv�Ɓu���v�͓�̕�����
���������������ŁA�[�z�̋�ƑΉ������邽�߂ɑO�̋�ɒ��������Ă���K�v��
�Ȃ������̂��B�����l����ƁA��Z��͏����₵������ǂ��A�����A����̐���
�h�g���Â��Ɍ��߂Ă����i�Ƃ��Ă悢���ƂɂȂ�B
�@���̂Ƃ��h�g�͘Z�\�܍B�����̍ʼnʂĊC�쓇�ɂ����̂͂����֗����ꂽ����
�ł���B�ߐ��̂悤�ȑv��ɂ�����������A�����֗����ꂽ�l�̒��ɂ̓}�����A��
����ĉʂĂ��l�������B��̊|�����͒߂���̂����i���D�܂ꂽ���Ƃ�������
���A���́A��O��ɏo�鉍���߂�������h�g�̐S���Ƃ炦�Ă���̂ł���B
���������ɖk�����֓n�鉍�͉������Ȃ�Ζk�A���Ďq��Ă�����B
��O�E�l��́A���m�̂��Ȃ��y�n����̖k�A�s�̊肢��\�����Ă���̂��B
�h�g�́A���N1101�N�Ɏ͖Ƃ��ꂽ����ǂ��A�k�A��r��ŖS���Ȃ����B
���̎��ɏD�����Y���̂͂�ނ����Ȃ����낤�B�������킽���́A
���N��������Ȃ��������̂��Ȃ₩�Ȑ��_�����K�������Ǝv���B
�@�֑���t��������A�N�̊|�����̋�́A���́u�t����я��X�ԁA
�H�������ƁX���v�Ƃ����T�̌��t�������̂��A��@�U���A��̋�̌����݂�
�u�ԁv���u��v�ɕς��Ċ��|�����̂��Ƃ����B����Ƃ���Ԃ�����A
�Ƃ����H�v���낤�B���́u�t����я��X��v�̎��́A�\��Ƃ̏����̏���
�������銵��ɂȂ�A���ꗈ�ĉY�̓ω��Ɋ|�����Ă���B
�@���āA�J�������ē��C�ɔ��g�𗧂Ă�����̓앗�������āA������
��z�����̏t�ł������B
�ܓ��Ȉ�N����
�@������玍��̗тɓ����ėV��ł��������A�����A�h�����̎��ɘa����
�l������̕������a���o�����B
�@�@�@�@�@�V�A�����V�U���@�@�C�����E�����
�@�@�@�@�@�ߊ��ېA���Ó��@�@���z�o�R������
�@�@�@�@�@�t�C���Y�뗧�@�@���t�g�~�Β��|
�@�@�@�@�@�z�ߔN�X�y�l���@�@䑓��X�V�V�{��
�@�@�@�@�@�@���F����i����終͉ƎR�j�B��O�E�l��i�ېA���ɋ��J���邱�Ə��� ���j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@��Z��i�Β��͖ڔ��A�Ԃ���Ƃ͌��炸�j�B�掵�E����i������ł���߂̂Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@���˂̗V�y)�B
�@�l����m��Ȃ��V�U�̖�l�́A���̂܂˂��Ƃ����Ă����ς�炸���������A
�P�݉����ĉ̂����Ƃ����ł��Ȃ��B���ÂȐ������̓����e�[�j���̊��߂铿�ڂ����A
�C���^�[�l�b�g�������A�o�R�͕����ŃS�[�^�}�E�u�b�_���C�s���I���ĎR�����肽���ƁA
������y�̓�����͓��̖�A�ƁB�킪�������C�ɖʂ����݂ɖ��̎R���݂�]��
���Ƃ�\��������A�v����������������n���r�����ɋ߂Â����B
�@�@�@2019�N�J���̌�Asuper full moon hidden by clouds
************************************************************************
�@78�@�킽������炷�Љ�
************************************************************************
�@77�@�V�����n���w�I�����
************************************************************************
�@76�@�C���̖k�ւ̗�
************************************************************************
�@75�@�I�́@�V�����Ñ�j����
************************************************************************
�@74�@�����j�����L�q����600�N��̘`��
************************************************************************
�@73�@�����j�����L�q����500�N�܂ł̘`��
************************************************************************
�@72�@�Δn�g���̊閦
************************************************************************
------- �������ɂ���ɂ������ā@------------
�@�킵�����{�����̓`���d���A����܂Łu���̎G�L���v���c�����̕����ɂ���
��������ǂ��A��70�b���牡�����ɂ��邱�Ƃɂ����B�K�������߂�\�L�́A���{���
�C���������Ԃ�ς��邱�ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B�����A�����ʂ̒P�ʂ��L������
���[���b�p�̌��t��\�킵���肷��ւ��l�����Ă������邱�Ƃɂ���B�K���A������
���������͏c��������ɂ��Ή��ł���B�ێ�I�Ȑ��{�ł����������Ă���̂�����A
��ʂ̕\�L�ł������������ׂ��������̂��B�|�ȁE�؊Ȃ�m��Ȃ��V�l��
�d�q�����ɐe���ގ���ɂȂ����B�V���͂������A�`����w���������l�搶�����A
���E�̕����Ɍނ���̂ɁA�c�̂��̂����ɂ��邮�炢�̂��Ƃ͂��Ȃ�������Ȃ�
���낤�B����ŕ��͂̕i�i��������Ȃ�債�����Ƃ͂Ȃ��̂��B����Ȃ��Ƃ�
�C�ɂ��Ȃ��Ă����ދC�y�Ȓ��́A�����珄���Ă������q�̌`���ɂƂ܂ǂ�Ȃ��B
�G���������āA��������ΉE��ōL���Ȃ��猩�邱�Ƃ��ł����͂��Ȃ̂��B
�@�����Ƃ��A�u�G�r���L�v�̕��͂Ƃ肠�������̂܂܂̌`�ɂ��Ă����B�킽���́A
B5�̑傫���̉������m�[�g����L���ɂ��Ă��āA�v���������Ƃ��L��
�G�r����������邪�A����������������͈�s�Ɏ��܂�B�Ƃ��낪�A�������
���������q�ɐ�������ꍇ�A���Â��Ɓu�݂��Ђƕ����v����s�Ɏ��߂邱�Ƃ�
�ނ�����������ł���B
************************************************************************
�@71�@V.�p���[�g�̘_���I�����I�Ȋw�̕��@
************************************************************************
�@70�@�C�T�̐l�ӓ��]�̐���������
************************************************************************
�@69�@�u���z�̓��v����T����{�̌Ñ�
************************************************************************
�@68�@�����ƒ��̑Θb�]�\
************************************************************************
�@67�@�u���z�̓��v�̗��j�n���w
************************************************************************
�@66�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̏\��@�I��
************************************************************************
�@65�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̏\��
************************************************************************
�@�t�^�@�E�B�g�Q���V���^�C���w�_���N�w�_�l�x�@��������
************************************************************************
64�@ �u���z�̓��v�̍l�Êw
************************************************************************
�@63�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̏\
************************************************************************
�@62�@�������E��܁@�u����Ƃ̓`���v�@PDF��
�@�@�@�@���̕����́A�ŋ߂��鋏�m�̕������猩�������Ƃ����B���Ƃ̎q�⑷�̂���
�@�@�@�ɋL�����o�������ƌ�����B���͂͏����d���ĉ��Ɍ����A�����Ƃ���̂�
�@�@�@�C���Ђ��邪�A�`���̕����Ɏ̂Ă�������������݂�����̂ŁA�Ƃ肠����
�@�@�@�u�������E��v�Ɏ��^���Ă����B
************************************************************************
�@61�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̋�
************************************************************************
�@60�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̔�
************************************************************************
�@59�@�����ŎЉ��T��@PDF��
************************************************************************
�@58�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̎�
************************************************************************
�@57�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̘Z
************************************************************************
�@56�@�푈���̓��L��ǂ�
************************************************************************
�@55b�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̌ܕ��
************************************************************************
�@55�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̌�
************************************************************************
�@54�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̎l
************************************************************************
�@53�@�����Ƃ����������鑶��
************************************************************************
�@52�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̎O
************************************************************************
�@51�@�ϓ����鎞��Ɛl�Ԃ�`�������w�@�\�@�w�閾���O�x
************************************************************************
�@50�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̓�
************************************************************************
�@49�@�����ƒ��̑Θb�@�u�F���ƌ���������āv���̈�
************************************************************************
�@�t�^�@�ʍ؉��r�n�N��2016
************************************************************************
�@38���@�@���ƉL���������炵���l�X�̂������@
************************************************************************
�@48�@�@�V���A�w�V���x��ǂ��@
************************************************************************
�@47�@�@�w�F���ƌ���̗��_�x���w���@
************************************************************************
�@46�@�@�������Ƃ����l�@
�@46b�@�@�������̎���ƐS���̐����@
************************************************************************
�@45�@�@���]�̎����@
************************************************************************
�@44�@�@�����i���_���l�����@
************************************************************************
�@43�@�@�ڊo�߂��l�̐����������@
************************************************************************
�@42�@�������E��3�@�@�����̐̌���@
�@41�@�킽���͂ǂ������҂��@
************************************************************************
�@40�@���i���č\�����邽�߂��@
************************************************************************
�@39�@������x�̃R�y���j�N�X�I�]���@
************************************************************************
�@38�@��������ꂽ�L�̋�z�@�\�@�L���ƈ��̓`���@
************************************************************************
�@37�@�Ƃ���ސ��_�����ǂ��@
************************************************************************
�@36�@���{���_�j�����ǂ��@
************************************************************************
�t�^�@�ʍ؉��r�n�N��2015
************************************************************************
29-2�@�������E������@�@������m�̕��� �@ PDF��
************************************************************************
�@35�@�u���Łv�Ɓu�j�q���Y���v������߂��@
************************************************************************
34�@�������E����@�@��̏�Ŏ��� �@ PDF��
************************************************************************
�@33�@�̑�Ȏt�ւ̎莆�@
************************************************************************
32�@���҂�q�˂� �@
************************************************************************
31�@���R�̐� �@
***********************************************************************
�@30�@���C�������o���S�����@�\�\�@�������ց@
************************************************************************
29�@�������E����@�@����m�̕��� �@ PDF��
************************************************************************
28�@��z���n���@�\�\�@�ېA���u�r�n�v�����̉ۋ� �@ PDF��
************************************************************************
�@27�@�ӎ��ɏ悹����
************************************************************************
�@26�@�s�P�e�B����
************************************************************************
�@25�@�n�[�o�[�}�X�̓N�w��������
************************************************************************
�@24�@�����̍����@�\�\����܂��Â��苦�c��ݗ�����
************************************************************************
23�@�w���[���b�p���j�x�\�@���{���j�̍��킹��
************************************************************************
�@�t�^�@�ʍ؉��r�n�N��2014
************************************************************************
************************************************************************
�@21�@�i�����R��ɗ���
************************************************************************
�@�@19���@�@�w�O���u鰏��x�u�G�ۑN�ړ��Γ`�v�̋����邱��
************************************************************************
************************************************************************
19�@�����O���A�O�蔶�@
************************************************************************
18�@���E��Y�̊Ջp
************************************************************************
17�@���̂悤�ɏ����ꂽ�N�w
************************************************************************
16�@���C�s�����@�@
************************************************************************
15�@�C�s�����@�@
************************************************************************
�P4�@�~���
************************************************************************
�P3�@�w�������q�̐^���x�����������Ɓ@���Z�Z�Z�N��̘`��
************************************************************************
�P�Q�@�Y�̍�
************************************************************************
�P1�@�o��ǂދ���
************************************************************************
�t�^�@�ʍ؉��r�n�N���Z��O�@�@
************************************************************************
�P�O�@���_�u�����j���̋L���Z�Z�Z�N��̘`���v�@
************************************************************************
************************************************************************
�W�@������l�̈̑�Ȏt
************************************************************************
************************************************************************
�U�@�l�G�A���ɐV���Ȃ�
************************************************************************
�T�@�Ӗ��̐[�݂�
************************************************************************
4�@���̍s����
************************************************************************
3�@����̖�
************************************************************************
2�@�l���`���ꂱ��
************************************************************************